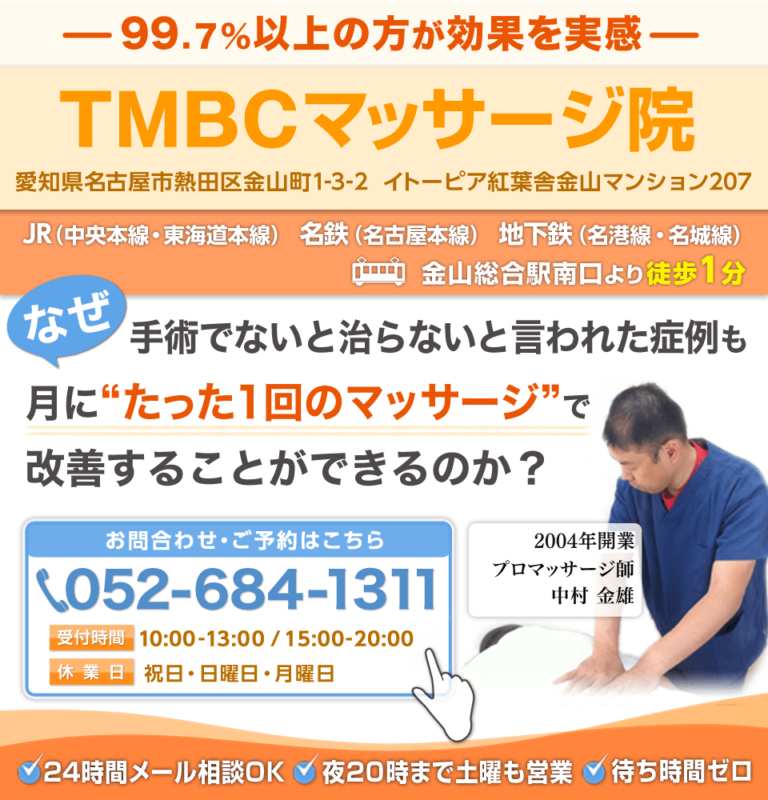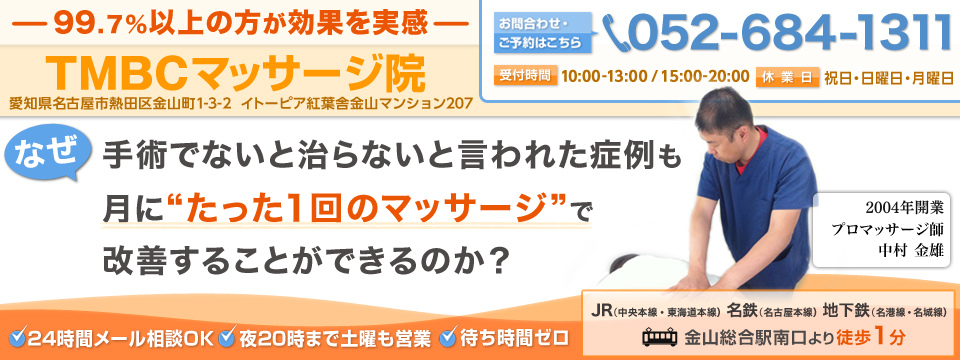腰痛の異常反応を知覚する検査
診断の重要性を考える
検査により腰部周囲(体)に起こっている異常反応を知覚することは異常の特定であり「診断」と言える。診断することは、来院された方の不安を払拭する大切な医療と言えるであろう。検査には問診、視診、運動検査、触診などがある。問診、視診、運動検査について、最新の検査機器を使用せずとも、映像化もしくは数値化することは可能である。例えば、体の絵に自覚症状のある所に印を付ける、痛みや悩みの度合いを1~10段階のどの段階に相当するか確認する、関節可動域の範囲を比較するなどである。これらの検査は最新の検査機器を使用せずに映像化もしくは数値化する代表的な方法である。このような映像化もしくは数値化することは、来院された方の状態を他者と共通認識するために必要な検査であると言える。
触診を数値化する
触診についても、圧痛点の有無、麻痺の範囲、熱感や冷感の度合いなど触知した内容を記すことによって検者と第三者との間に共通の認識が可能となる。また、触知した部位の異常反応を5段階や10段階の度合いを利用し記録することで、異常反応の存在や度合い、異常反応の変化なども第三者間と情報共有が可能と考えられる。
数値化した触診の問題と信憑(信頼性)
ところが、触知したことを数値化することについて問題もある。相手の体に起こっている異常反応の数値化には「異常反応を正確に数値化すること」が前提にある。知覚した情報は、知覚した本人だけの情報とも言える。ここで考える問題とは、知覚した本人だけの情報が共通した情報として他者との共有が可能か、という問題である。
触知した感覚は知覚した個人の感覚であり、この知覚した感覚そのものを他者と共有することはできないと考える。しかし、知覚した感覚は、知覚した本人にとって確かな感覚である。施術前と施術後とで施術者が触知した異常反応を、施術者本人の感覚で数値化し、この数値を比較することで触知した変化の度合いを第三者と共有することは可能と言える。また、施術者が触知した異常反応の数値の変化と患者の訴える症状の数値の変化とが同調していれば異常反応を確かに認識していると考えられる。
当院で行っている触診の数値化
患者の痛みや施術者の捉えた異常反応という知覚そのものの共有はできなくとも、数値化することで、施術者と患者の変化の度合いを比較することで、施術効果の共有が第三者にも共有することができるのである。
当院では、患者さんには0~5段階による自覚症状の度合いを示していただいています。また、施術者も0~5段階による異常反応の度合いを記録し、それぞれ施術前と施術後を比較し、施術効果の「見える化」を実施しています。