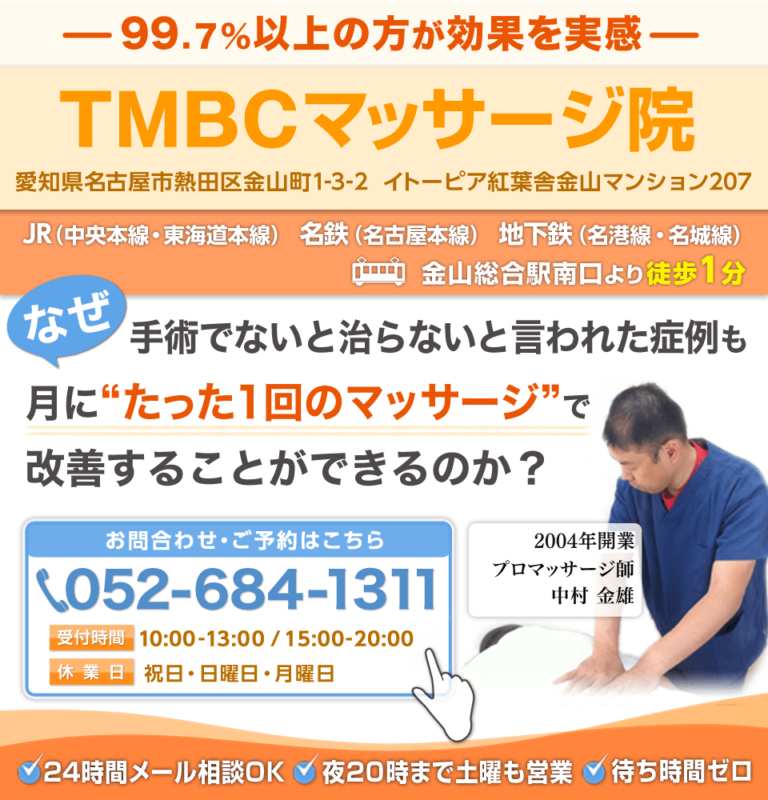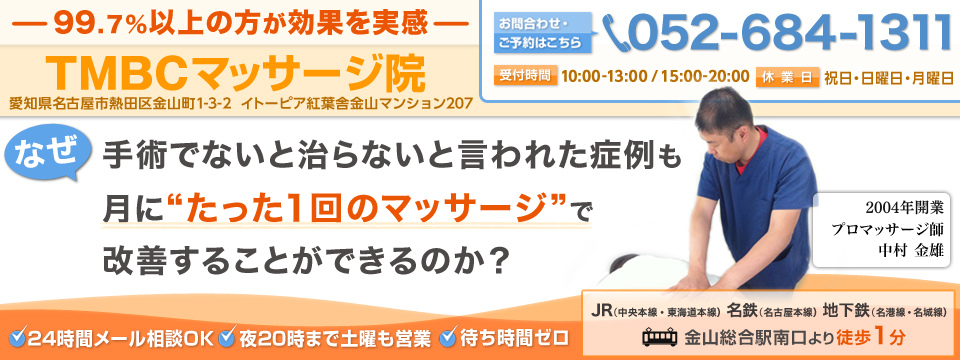施術者間における知覚の共有方法を探る
『感じる』を考える
知覚(触圧覚、視覚、嗅覚、聴覚、味覚など)には個人によって大きな差が生まれることがある。この知覚の違いは、肉体的な発達の違いから考えられるし、環境の違いによっても考えられる。
私たち人間は、多くの情報を視覚によって得ている。そのため、視覚に頼りがちと言えるであろう。マッサージ、指圧など、指先の知覚によって施術を行う施術者が視覚で施術対象の情報共有を行うことは可能であろうか?このことを考察する前に、あん摩の歴史を考えていきたい。
あん摩の歴史
あん摩を生業とする人々は、指先を中心とした知覚により、患者の皮膚の変化(発汗や体温など)、患者の息遣いなど微妙な差異を触知してきたと考えられる。そう考えるのは、あん摩業は目の見えない(盲目)人々によって行われてきたためである。この事実の歴史は、視覚以外の感覚によって施術が可能である、と言っている。さらに、多くの盲目の方が施術者として活躍していた背景もあることから、施術には視覚以外の感覚に重要な要素があるとも考えられる。歴史的背景から、触圧覚や聴覚など視覚以外の感覚によって患者の体から情報を認識していたと考えられるのである。
現在の科学による感覚共有方法
次に、視覚以外の感覚を第三者と共有するための方法は何であろう?と、このような疑問が現れる。人間は視覚に頼った活動を行っている。その関係上、第三者と情報共有する方法の多くは視覚を利用している。現代医学でも視覚でわかる映像は重要視されている。また、数値化することでも情報共有は行いやすい。誰もが一目で納得できる、すなわち「百聞は一見に如かず」という映像化、数値化といった情報共有方法が現れて以来、人は映像や数値の検査に頼ることとなってしまった。その結果、それ以外の検査方法を軽んじる傾向になったと言っても過言ではない。現に、近代医学が流行し始めた近年では、経験医学である東洋医学を野蛮な医学と表現されることもあった。東洋医学の歴史を振り返ってみれば、眉唾ものの伝承もあったであろう。しかし、皆が確信できる伝承もあったはずだ。一概にすべて野蛮と切り捨てず、よいものはよい、という考えで東洋医学と近代医学と融合した方が有益であろう。
人類の歴史の総まとめとしての感覚共有
このような考えに至れば、古くから伝承される技法に経験的な信憑の高いものの存在があると言える。口伝により伝わってきている技法を現代の文字にすることこそ、視覚による情報共有の第一段階と言えるのではないか。文字の内容に映像も加われば更なる情報の強度が増すのだが、現在の科学技術では腰痛の映像化はなされていない。先に問いに答えるなら、科学技術の段階で映像化による情報共有は難しくとも、文字や数字によりある程度の情報共有は可能と言える。①言葉による情報共有、②言葉を文字に変換した情報共有、③言葉を数字化した情報共有、これらの方法が現在における情報共有であろう。
【痛みの認識段階】
- 自分だけの痛み、個人的な痛み(思い込み、心の問題など)
- 二人以上が共有している痛み(科学で証明されていないが経験のある痛み、筋痙攣、筋肉痛など)
- 視覚により共有できる現象を持つ痛み(骨折、脱臼、筋断裂など)
【変化の認識段階(施術者視点)】
- 自分だけの感覚(想像、想起)認識(思い込みなど)
- 二人以上が共有している感覚変化(可動域増加、感覚が変化した瞬間の共有など)
- 視覚により共有していた痛みの現象そのものの修復(骨折回復、脱臼の修復など)